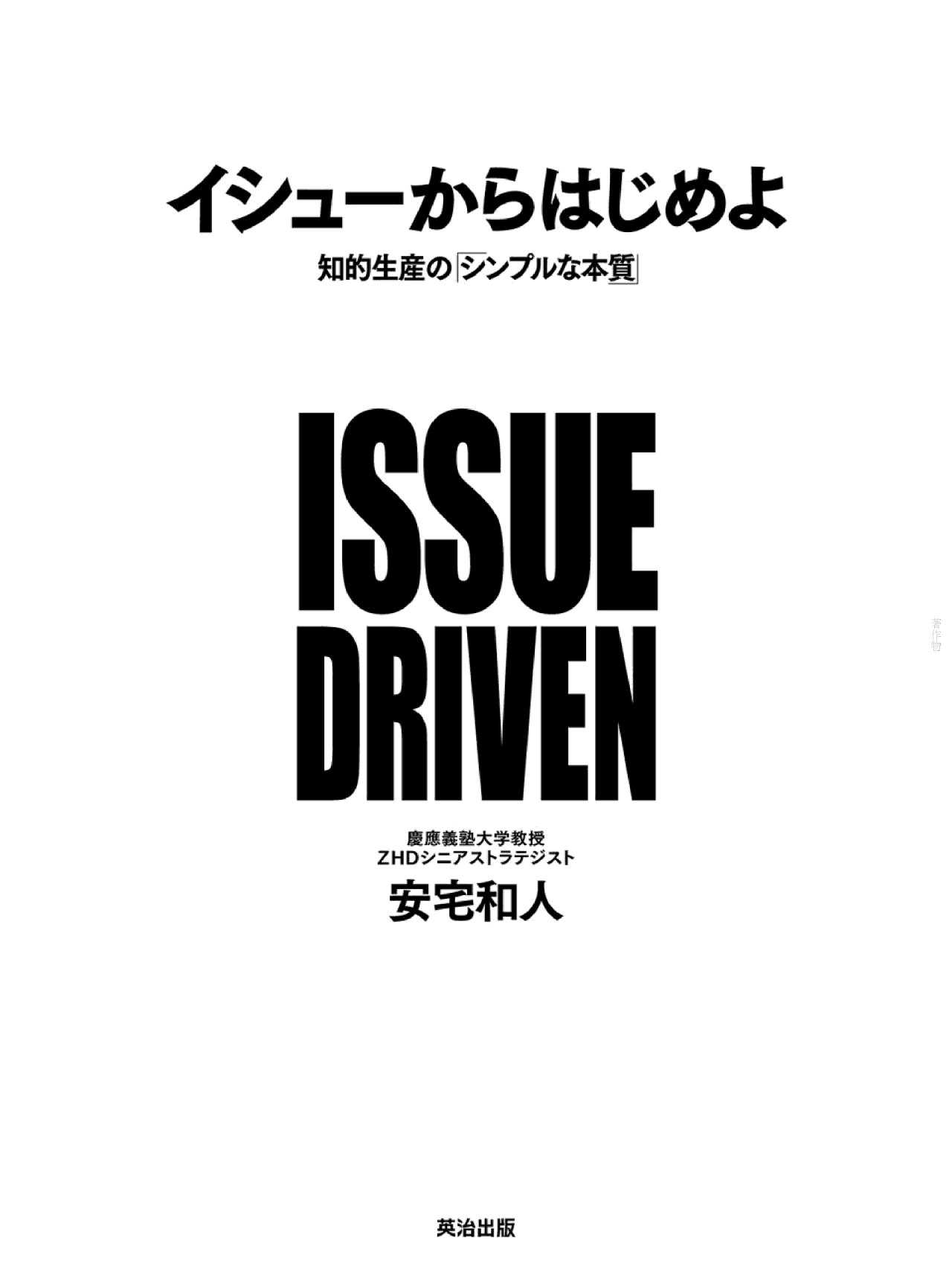
今回読んだのは第1版です。これから読まれる方は改訂版が出ているのでそちらをどうぞ。
基本情報
タイトル :イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」
著者 :安宅 和人
発行所 :英治出版株式会社
初版発行日:2010年12月11日
ISBN :978-4-86276-085-2
タイプ :ソフトカバー
目次情報
- 優れた知的生産に共通すること
- 序章 この本の考え方―脱「犬の道」
- 常識を捨てる
- イシュードリブン―「解く」前に「見極める」
- イシューを見極める
- 仮説を立てる
- よいイシューの3条件
- イシュー特定のための情報収集
- イシュー特定の5つのアプローチ
- 仮説ドリブン①―イシューを分解し、ストリートラインを組み立てる
- イシュー分析とは何か
- STEP1 イシューを分解する
- STEP2 ストーリーラインを組み立てる
- 仮説ドリブン②―ストーリーを絵コンテにする
- 絵コンテとは何か
- STEP1 軸を整理する
- STEP2 イメージを具体化する
- STEP3 方法を明示する
- アウトプットドリブン―実際の分析を進める
- アウトプットを生み出すとは
- トラブルをさばく
- 軽快に答えを出す
- メッセージドリブン―「伝えるもの」をまとめる
- 「本質的」「シンプル」を実現する
- ストーリラインを磨き込む
- チャートを磨き込む
- おわりに「毎日の小さな成功」からはじめよう
- 謝辞
個人的評価
超個人的に独断と偏見を多分に含む評価を星5段階で表します。
▶オススメ度
論文やプレゼンテーションなどを作る機会が多い方は内容を理解し筆者のメッセージを受け取ることができるかと思う。概念的な説明が多く私にはなかなか具体的にイメージすることが難しかった。人生経験を重ね何度か読み返すことで筆者が伝えたいメッセージを正しく受け取ることができるのだろう。
▶よみやすさ
読み進めていくうちに徐々に難解になってきて、なかなか理解が追いつかなくなってしまった。まだまだ私ではこの本の本質を理解するには頭が足りなかった。文章の理解で精一杯で内容のイメージまで追いつかなかった。
▶専門性
直接的に難解な専門用語が並んでいるわけではないが、全体として前提とている基礎知識は高いように感じる。
▶読後感
学がないせいか読み進めていくうちに置いてきぼりにされている気になってしまった。この本を理解するにはあまりにも知識が無さ過ぎた。
こんな方におすすめ!!
- ビジネスマン
- 論文などを書く人
どんな本??
序章では、前提となる用語の考え方を整理している。読者と用語の認識を合わせることで正しいメッセージを送れるようにしている。意味のある仕事「バリューのある仕事」とは何なのか?どうすればバリューのある仕事を増やすことができるのか。そのためにはイシュー度を意識する必要があると解く。「イシュー度」とは「自分のおかれた局面でこの問題に答えを出す必要性の高さ」と定義している。別な言い方をすれば必要性の高い問題に取り組むことがバリューのある仕事に取り組むということといえるのではないだろうか。そして「解の質」により「バリューのある仕事」ができているかが決まる。
1章では、イシューを見極めることの大切さを解いている。そのためにまず仮説を立て答えを出すべきイシューを明確にする。そしてイシューが見えてきたらそれを言語化する。良いイシューの条件を3つの条件を提示し、各条件について説明している。しかし、良いイシューを見つけるのは簡単ではない。そのためにイシューを特定するための情報収集法、アプローチ法について解いている。
2章では、イシューが特定できたら次にやることは「ストーリーライン」づくりと「絵コンテ」づくりによる「イシュー分析」である。問題提起ができたらストーリーラインを作る。ストーリーラインづくりは2つの作業からなり、1つはイシューの分解、もう一つは分解したイシューに基づいてストーリーラインを組み立てる。その方法について詳しく説明している。
3章では、分析イメージづくりの作業であ「絵コンテ」づくりの勘所を紹介している。「どんな分析結果がほしいのか」を起点に分析イメージをつくるとのこと。絵コンテづくりには3つのステップがある。「軸の整理」「イメージの具体化」「方法の明示」でありそれぞれのステップについて説明している。
4章では、実際に分析に入る。分析は本丸のイシューからではなくまずサブイシューから始める。イシューの分析は答えありきではなく、フェアな姿勢で検証しなければならないと解く。イシューからはじめるとき答えありきでの分析に陥りがちであるとのこと。
5章では、仕上げとしてまとめの作業について解説している。仕上げ段階では「本質的」と「シンプル」の視点で磨き込を行うとのこと。エレベーターテストという観点は私にはなかったが、確かに人に説明するときに要点をまとめて完結にすることが重要である。そこまでできてようやく理解できているといえるのだろう。そしてプレゼンテーションで使用する図表についてブラッシュアップする必要性については私としても痛感する。ただ空間を埋めるだけの図表も少なくない。しっかりとメッセージを伝えられるように細部にまで気を配りたいところである。
個人的気づき・印象に残った言葉
イシュー、つまり答えを出すべき問題
そもそもイシューとは何なのか。イシューとは答えを出すべき問題のことである。そして喫緊に答えを出す必要のあること。
定量分析には、「比較」「構成」「変化」という3つの型しかない
表現方法は無数にあるが大元の型は3つとのこと。確かに定量的なものの分析はこの3つでなりたつだろう。この事実を知り理解することで日頃の分析が楽になるとのこと。
最後に
表層的は課題は分かってはいるが本質的なイシューとなると見極めることは簡単ではない。だからこそまずはしっかりとイシューを見極める能力を身に着けたいものである。これが課題だと思っても本質的に解決しなければならない問題や課題は別なところにあるというのは往々にしてあることである。
お読みいただきありがとうございました。
拙い紹介でしたがいかがでしたでしょうか?
記事はあくまでも未熟者である私の感想になりますので、ぜひあなた自身で本をお読みいただき、どのように感じたのかをコメントいただけると嬉しいです。
あなたの読書ライフのお役に立てていれば幸いです。

コメント