
タイトルとカバーのイラストに惹かれて購入
副題のAI時代のアンラーニングが示す意図も気になるところである
基本情報
タイトル :冒険の書
著者 :孫 泰蔵
発行所 :株式会社日経BP
初版発行日:2023年2月22日
ISBN :978-4-296-00077-7
タイプ :ソフトカバー
目次情報
はじめに
父からの手紙
第1章 解き放とう|学校ってなんだ?
- ある冒険者のお告げ
- 200年つづく呪文
- パノプティコンの憂鬱
- 再発見されるべき発明
- 縛りを解き放て!
- スローな学びにしてくれ
- 基礎という神話
- 失敗する権利
- 1章のまとめ
第2章 秘密を解き明かそう|なんで学校に行くんだっけ?
- ザ・グレート・エスケープ
- 3つに分けられた悲劇
- 暴かれた秘密
- タブラ・ラサ
- 子どもは子ども?
- 子どもを書物でいじめるな
- 守れれる存在にサヨナラを
- 2章までのまとめ
第3章 考えを口に出そう|なぜ大人は勉強しろっていうの?
- 能力という名の信仰
- 循環論法のトリック
- 才能は百害あって一利なし
- 優劣のlineを越えて
- I + E = M
- 学力なんか身につけてどうするの?
- 異なる点と点を結ぶ
- 3章までのまとめ
第4章 探究しよう|好きなことだけしてなぜいけないの?
- 車輪の「無意味」
- 無用之用
- 悪人正機のカミソリ
- 答えるな、むしろ問え
- つくるとわかる
- 専門家と素人
- 4章までのまとめ
第5章 学びほぐそう|じゃあ、これからどうすればいいの?
- 親の言うことは聞くな
- なにがしたいかわからない?
- ギブ・アンド・ギブン
- もし、明日死ぬとして
- 世界を変える魔法
- 螺旋に連なる小さな弧
- ライフロング・アンラーニング
- 後世への最大遺物
- 5章までのまとめ
おわりに 新しい冒険へ
旅の仲間たちへの謝辞
世界に散らばる冒険の書たち
本書の問い
参考文献
個人的評価
超個人的に独断と偏見を多分に含む評価を星5段階で表します。
▶オススメ度
個人的には作者の主張を100%受け入れることはできないが、教育について気づきや考える機会を与えてくれている。著者がこの本で主張していることを心から言っているのであれば自分の子どもには学校に行かせないのだろう。遊ばせるだけ遊ばせ学びたいと思うまでただ待つのだろう。それか子どもでありながら働きに出すのだろう。
▶よみやすさ
多くの偉人が出てくるが堅苦しいわけではなく、ストーリー仕立てになっており本に引き込まれる作りとなっている。
▶専門性
多くの歴史上の偉人が登場してその人がなし得たことや発明したものなどを紹介してくれている。個々は具体的に掘り下げて説明はされていないが参考文献を丁寧に紹介しており興味を持った分野や内容について掘り下げて調べられるようになっている。
▶読後感
本で語られていることは比較的偏った思想に感じられ、筆者の主義主張に賛同できない部分も出てきた。
どんな本??
ストーリー仕立てになっており第1章では、書の作者(親)が冒険に出かける導入部分である。教育とはなにか、なぜ人間は学ばなければならないのかを偉人を交えながら解いている。現代の教育論に一石を投じている。19世紀のパノプティコン状の刑務所から始まり人間は人間を服従させる仕組みを編み出してきた。学校もその一つであると解く。そして、イギリスの学校教育のルーツを紹介してくれている。それは工場のような仕組みそのものであると。効率よく教育を受けることができるようになったことの意味は大きいが、その方法が現代でも変わらないことに疑問を呈している。
第2章では、学校という場についての考えを示している。本来一つだった「遊び」「仕事」「勉強」がいかにして区別されるようになってきたのかを示し、いつしか「遊び」が「エンターテインメント消費」されるものになっていったと解く。真実かどうかはわからないが17世紀より前は大人と子どもととの区別はなかったとのこと。17世紀以降大人と子どもの区別が生まれ子どもを子ども扱いすることにより制限されるようになってしまった。そもそも教育とは何か、教育とは学習する習慣を身に着けさせることであると解く。
第3章では、能力について考察している。そして能力と勉強との関係を示している。「能力」とはあくまで「結果論」であると解く。「能力」のあるなしは「結果論」と「比較論」によって生まれたフィクションであるとのこと。個人的には、結果を出し他人よりも良い成績を出した人を、「能力」があるとすることは結果論と比較論によるフィクションであるという主張はいささか暴論だと思う。
第4章では、ものの価値や意味について解いている。効率化が望まれる現代において人々のものごとへの視野はどんどん狭くなっている。意味のないことに意味があるようなものの見方をする余裕は現代人にはないのかもしれない。「評価」や「査定」が「同調圧力」を生み自由に生きることを阻害していると解いている。
第5章では、人生の選択について解いている。人生の岐路に立つとき親の期待や周りの目をどうしたって気にしてしまう。しかし人生の選択は自分で考え決めなければならない。資本主義の下で形成された価値観は人間が本来持っている価値観とは異なる。歪められた価値観を取っ払い人間本来の価値観で判断できるようになることこそ本当の自由であるとのメッセージを示している。
個人的気づき・印象に残った言葉
学習する習慣こそが教育
社会に出ると学習はおろか本すら読まなくなる人間が多い。学ぶことは学生だけの特権ではない。常に学ぶことが大切なのだ。学生時代にその習慣を身に着けられないことは生涯を通し不幸なことなのだろう。
最後に
私の子どもが通う保育園でも「子どもの選択を尊重する」として子どもを好き勝手させる親がいるがそれはあまりにも無責任ではないだろうか。それに通づる違和感を読んでいて感じていた。選択を指せる前に教えなければならないことがあるのではないだろうか。何も知らない子どもに対し選択を強要し好き勝手させるのは育児放棄に近いと思う。教育のあり方や向き合い方などについて考えさせられる内容となっている。読書自体、本に書かれていることがすべて正しいと受け入れるのではなく是々非々で良いものは受け入れ、違うと思う意見を持つことも大切であろう。古い価値観に凝り固まっているせいかこの本の主張通りの世界が幸せに発展しているとは到底思えなかった。
お読みいただきありがとうございました。
拙い紹介でしたがいかがでしたでしょうか?
記事はあくまでも未熟者である私の感想になりますので、ぜひあなた自身で本をお読みいただき、どのように感じたのかをコメントいただけると嬉しいです。
あなたの読書ライフのお役に立てていれば幸いです。
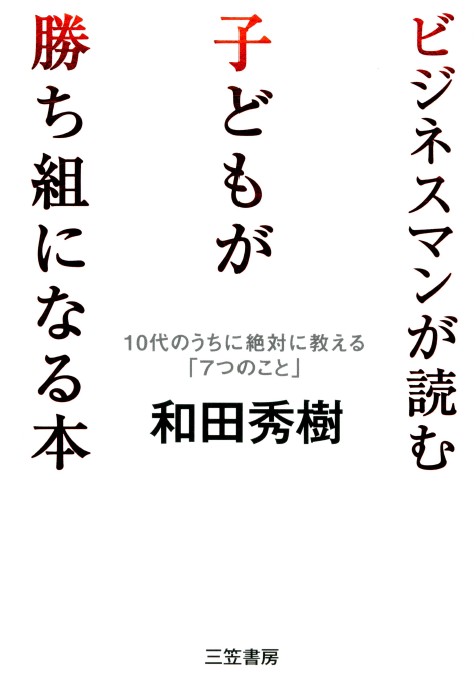
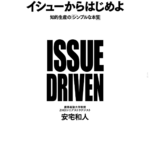
コメント