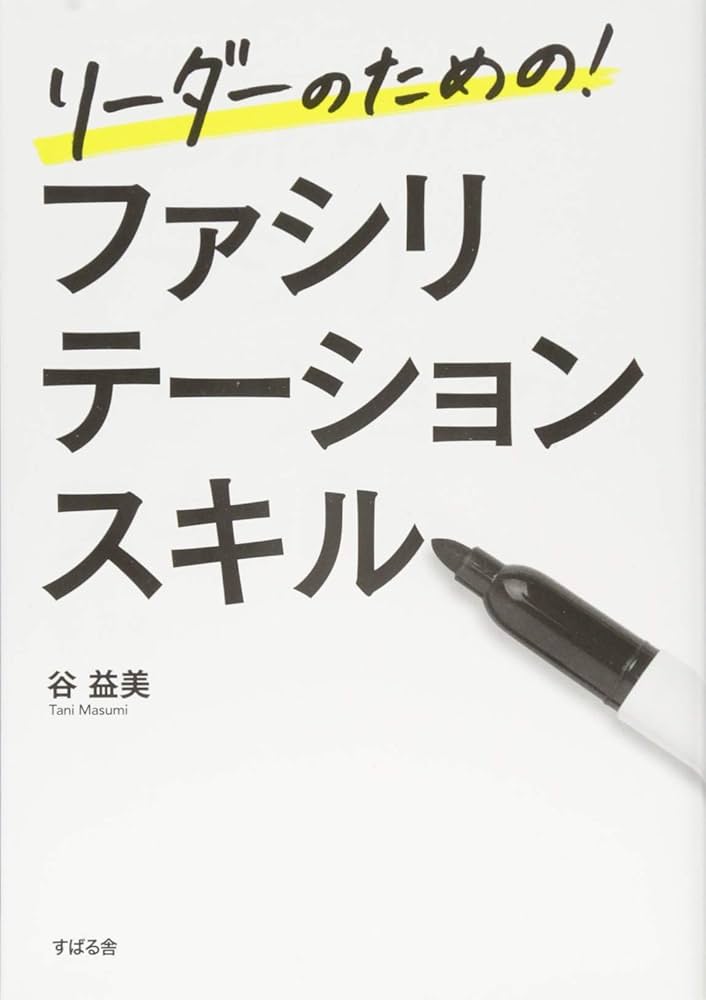
コミュニケーションスキルの低い私がどうすれば有意義なコニュニケーションを取ることができるのかを学びたく購入。
自分がいるチームがどうすれば有意義に動けるようになるのかを知ることで生産性の向上を図っていきたい。
基本情報
タイトル :リーダーのための!ファシリテーションスキル
著者 :谷 益美
発行所 :株式会社すばる舎
初版発行日:2014年7月31日
ISBN :978-4-7991-0333-3
タイプ :ソフトカバー
目次情報
- プロローグ
人の集まるところ、ファシリテーションあり
- これがリーダーのファシリテーションスキル
- チームの力、引き出せていますか?
- 最強チームを作り出す2つのスキル
- ファシリテーティブなリーダーになろう
- ファシリテーション基本のキ。大切なのは「個別対応」
- メンバーがどんどん話したくなる空気を作る
- まずはこれだけ!
チームを回すファシリテーション- チームのコミュニケーションを仕組み化する
- 対立・停滞・重複が消える。ホワイトボードはこうして使う
- 意見や気づき。どんどん引き出す質問のコツ
- 結論が出ない理由と出す方法
- 決めたらやろう。メンバーのやる気の引き出し方
- ここからが本番!
ビジネスを回すファシリテーション- ビジネスの成否はファシリテーション次第
- 初対面だらけの会議。大づかみに相手を見極める
- 対話はこうして生み出そう。声かけ仕かけできっかけ作り
- 量も質も欲張りに!アイデア出しのブレインストーミング
- もっと議論が深まる・広がるホワイトボードのスキルって?
- 会議の進行役を超えて。プロジェクトを回すための極意
- 日常の枠を超えて!
いろんな人が集まる場はこうして回す- 全社レベルで組織活性。研修会や大会議
- 多様な意見に学ぶ。パネルディスカッション
- 体験を通して語り合うワークショップ
- 飲み会だって、ファシリテーション!
- 何が生まれるか楽しみ。交流会をやってみよう
- 大人数でやるなら。簡単便利なワールドカフェ
- エピローグ
「ファシリーダー」が世界を変える!
個人的評価
超個人的に独断と偏見を多分に含む評価を星5段階で表します。
▶オススメ度
ファシリテーション入門書といった内容で、技術面よりもコミュニケーションの重要性を説いている
▶よみやすさ
文章自体は読みやすく、専門用語も出てこないため読んでいて難解な部分はなく、まさに入門書といった感じの本
▶専門性
理論やフレームワークについての説明もしており、幅広く知識を得ることができる内容となっている
▶読後感
この本を読んでファシリテーターとして自信を持てるといったものではないが、コミュニケーションの重要性を改めて再認識させられた
こんな方におすすめ!!
- 新たにリーダーに任命された方
- リーダーとしてチームの能力を引き出せていないと感じている方
- ファシリテーター入門者
どんな本??
第1章では、ファシリテーションスキルの重要性を説いている。ファシリテーションスキルを用いることで成長を促し成果をあげられるチームを作ることができる。そのためにリーダーに必要なファシリテーションスキルを示している。いちメンバーでいるうちはリーダーに対しアピールする。自分はこんな人間だ、こんな能力がある、こんな成果を出した、・・・。リーダーは逆にメンバーのことを「知る」ことからコミュニケーションが始まると説く。
ファシリテーションはなにも会議やミーティングのときだけの話ではない。リーダーはファシリテーションスキルを活かし1対1のコミュニケーションでチームの士気を高めることができる。その方法を示している。
第2章では、ミーティングについて説明している。ビジネスは多かれ少なかれミーティングで回っている。ミーティングの仕方についてタイプ別で説明している。意外と曖昧なままミーティングが行われていることがあるかと思うが、ルールを決めて共有することが必要と説く。
そして、ミーティングの運営について説明している。ホワイトボードの使用方法、意見を引き出すための質問力、ミーティングの目的・ゴールの設定と共有の重要性などを説いている。
第3章では、会議を回すテクニックを説いている。テクニックを駆使するにも会議の目的によって使用するテクニックも変わる。まず会議の目的、種類を整理している。テクニックの一つとして紹介されている「ソーシャルスタイル理論」は人の傾向を分類したもので、会議のみならず日々のコミュニケーションでも役に立つ内容である。その他、企業経営戦略でも使用されているようなフレームワークについても説明してくれており、ファシリテーションにとどまらず幅広い知識を得ることができる。
第4章では、より大規模な研修会や会議についての運営について説明している。一辺倒な会にならないためにはどうすればよいかのヒントを示してくれている。その他、ディスカッションや会社での飲み会などをより有意義にするための提案がなされている。
個人的気づき・印象に残った言葉
「引き出して、まとめる」のがファシリテーション。
会社での会議で意見を引き出すことはなかなか難しい。メンバーで意見を出し合い納得を得て推進していく方法を習得することでチームの能力を何倍にもすることができるはずである。
人は期待され、納得して動きます。
ともするとリーダーは自分の気持ちや思いをメンバーが理解してくくれているものと思いがちである。期待や思いは言葉にしなければ伝わらない。言葉にしたところで全部は伝わらない。自分は期待されている、これには意義があると思うから人は前向きに取り組むことができる。
最後に
コロナ禍以降リモートワークの推進もあり、会社でのコミュニケーションも変化している。しかし、やはり人間同士のコミュニケーションは対面が基本である。チャットやメールの文章だけでは伝わらないものもあるし、直接対峙することで見えてくることも多い。
1対1のコミュニケーションが基本と説く本書の通りメンバー1人1人との関係性向上を図っていきたいと考えさせられた。
お読みいただきありがとうございました。
拙い紹介でしたがいかがでしたでしょうか?
記事はあくまでも未熟者である私の感想になりますので、ぜひあなた自身で本をお読みいただき、どのように感じたのかをコメントいただけると嬉しいです。
あなたの読書ライフのお役に立てていれば幸いです。

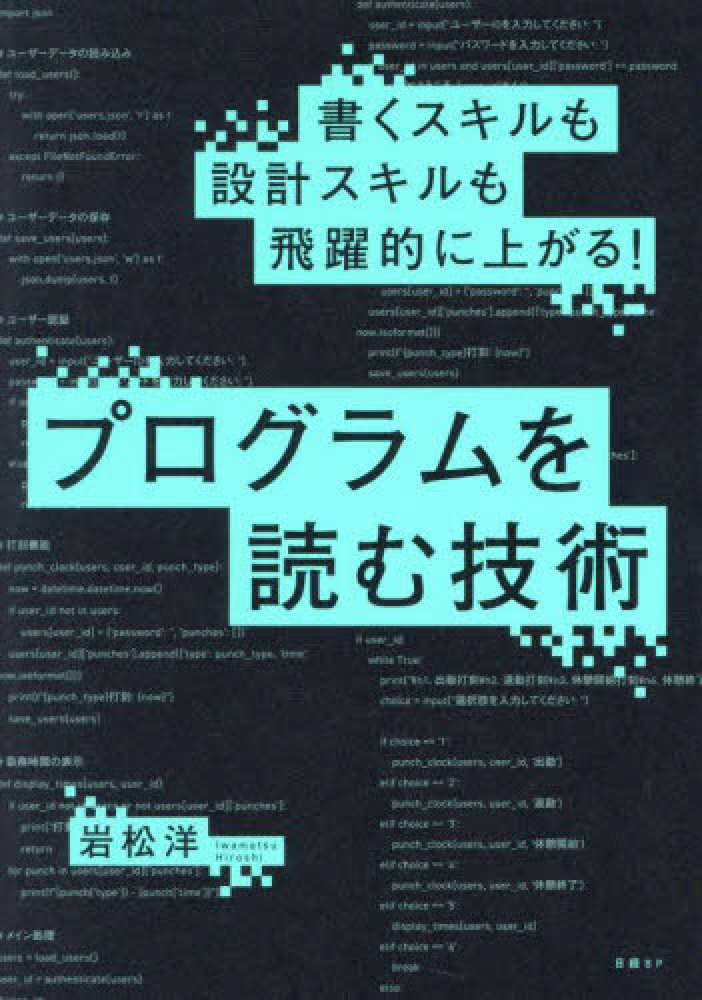
コメント